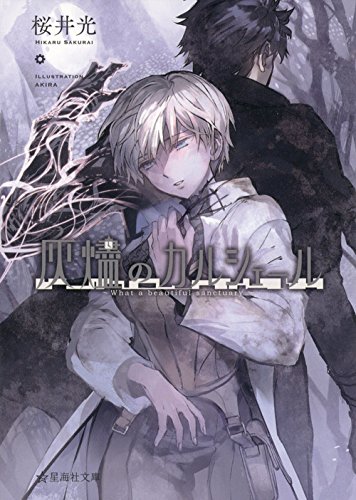『灰燼のカルシェール』感想。
最近、「オフビートで硬質なラノベ」というものに餓えていまして、その趣向に合致した作品というものを探していたのですが、漸く出会えました。その作品のタイトルは、『灰燼のカルシェール』。
バラード的終末世界観で、ファンタジーや現実、人種や立場の違いに関係なく、生き残った人間がしばしば見せる、まるで自分が引き起こした過ちの結果であるように振舞う、その一種の謙虚さが作品内に通奏低音のように漂い、死の気配とでもいうべきものが、その静謐で硬質な文章で描かれ、ぼくに人間の善意の在処を教えてくれる。えぇ、大好きです、こういう物語は。
PLOT
かつて、都市と蒸気機関は密接な関係を持っていた。生産と発展は同義であり、高度に発達した都市はその象徴にして中心、人間の歴史に恩恵をもたらすのはまさしく蒸気機関の役目だった。
工業のみならず農作業においても機関機械(エンジンマシン)の作業対象であり、19世紀の末には既に、人々の生活は蒸気機関なしには成立しえないほどとなっていた。だからこそ、機関都市とはある種の尊称でもあったのである。
ーー現在では、誰もそう呼ぶことはなくなってしまった。
数十万から百万もの人々を擁していたはずの、絢爛華麗な都市は、今やもう、廃墟でしかない。
異常発達した蒸気機関文明は、廃液や排煙を吐き出し、空と大地を穢した。蔓延した汚染物質は、本当の空、本当の海、世界を彩る青色のすべてを、永遠の灰色によって埋め尽くしたのである。
ーーそして、【世界の終わり】が訪れる。
灰色雲をまっすぐ引き裂き、惑星のあらゆる箇所へ飛来する三十三本の【円柱】、空を覆う黒い人型、海底から浮かび上がる朽ちた神殿、そこから這い寄る異形、機械で組成された巨人の群れ、砕かれる無数の兵器、引き裂かれる大地、鮮血の大河、逆さまに地面に埋め込まれる人々、呻き声を上げ蘇る機械死人。
空が死に、
海も死に、
人間も、犬も猫も、鼠も、昆虫さえも死に絶えた。
大地は黒く染まり、都市は廃墟となり、残されたものは、機械死人の呻く声だけとなり、
やがて、世界は静かになった。
これは、【邪悪の円柱】突き立ちし灰燼の世界に残された、最後の人間の物語である……。
Review
スチームパンク、なんと甘美な響きであろうか。ステレオタイプなツール、マッドサイエンティスト、それらのマテリアルの懐古感に廃墟探訪の浪曼、昔発売された『FRAGILE~さよなら月の廃墟~』というゲームが脳裏をよぎりました。あちらはスチームパンクではないけれど。廃墟探訪もあまり関係がない。
廃墟と化した遊園地、寂れた遊具、風化したお菓子や景品、かつて【夢の国】として人々を賑わせ、生きている人間が発する、たくさんの声と音で充ちていたはずのものの残滓。いいですねぇ。むかしむかしあったはずの規範の崩壊や価値の多様化という現実に目を瞑り耳を塞ぎ、ある種の亡霊に取り憑かれたように描かれる世界。死の気配が充ちています。
それは一歩間違えれば読者を暗い悪循環に導きかねない危うい規範なのですが【終末】という世界観によって回避している。崩壊した一定の確実だと思われていた規範を再建しようともせず、対立すべき障害もなく、ただ緩やかに死に向かっていく姿勢。好きですね。
もちろん終末世界観は間違いなく、残酷さや絶望の象徴です。なのにぼくはそこから善を学ぶことができる。生きることが何より困難な生活にあっても、未来が終わりを示したとしても、決して死ぬことを目指すことなく、人間の最良の部分である善性を見失わず、自分の生きる場所に到達するために力を尽くし、毅然と存在するふたりの“人間”。ぼくはその存在を確認できただけで、ただ、ただ、感動に打ち震えました。
そしてすっかり桜井光先生のファンになったぼくは、彼女の描いた<スチームパンクシリーズ>をすべてプレイすることを固く誓ったのでした。<終>